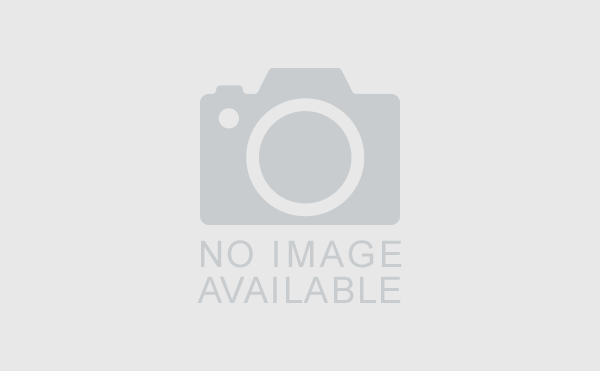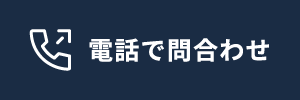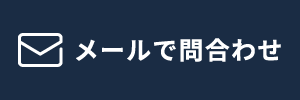後遺障害の等級と慰謝料
はじめに
交交通事故でけがを負い、治療を続けてもそれ以上症状が改善しない状態となると「後遺障害」として認定されることがあります。
この後遺障害に認定されるかどうかで、受け取れる慰謝料や損害賠償の金額が大きく変わります。
そのため、等級や基準を正しく理解することがとても大切です。
後遺障害の等級は1級から14級まで
後遺障害の等級は、最も重い「1級」から最も軽い「14級」までの14段階に分かれています。
等級が上がるほど、日常生活への影響が大きくなり、慰謝料や逸失利益も高額になります。
- 等級
- 主な内容
- 1〜2級
- 高次脳機能障害や常時介護が必要な重度障害など
- 3〜7級
- 視力・聴力の喪失、片麻痺など生活に大きな支障がある障害など
- 8〜13級
- 関節の可動域制限やしびれが残るなど、一定の不自由がある障害など
- 14級
- 頚椎捻挫(むちうち)等の神経症状が長期に残る場合など
ただし、これはあくまで目安であり、同じようなけがでも症状の重さや回復の程度によって判断が異なります。
むちうち(14級)や骨折(12級)の事例
後遺障害の申請で特に多いのが、むちうちや骨折による後遺症です。
- 頸椎捻挫(むちうち)
- 画像検査で異常が見られなくても、痛みやしびれが長く続く場合は、14級9号に認定されることがあります。
- 骨折による可動域制限
- 骨折後に関節の動きが制限されると、12級6号(片手や片足の可動域制限など)に認定される可能性があります。
どの等級に認定されるかによって、受け取れる賠償金の額が大きく変わるため、後遺障害申請の手続きは慎重に行う必要があります。
後遺障害の認定結果は、後遺障害診断書の内容や申請書の書き方によって大きく変わることがあります。
医師が作成する診断書は、必ずしも後遺障害の等級認定に有利な形で書かれるとは限りません。
そのため、申請の前に後遺障害に詳しい弁護士へ相談し、どのような点を伝えるべきかを確認しておくことをおすすめします。
慰謝料の金額は3つの基準で変わる
後遺障害が認定された場合、慰謝料の金額は「どの基準で計算されるか」によって大きく異なります。
一般的には、以下の3つの基準があります。
自賠責基準|法律で定められた最低限の補償
自賠責基準とは、交通事故の被害者救済を目的として法律で定められた最低限の補償額を示す基準です。
この基準で認められる後遺障害慰謝料は、
- 14級
- 約32万円
- 12級
- 約94万円
となっています。
あくまで被害者の最低限の救済を目的とした基準のため、実際の損害や苦痛に比べて金額が低くなることが多いのが特徴です。
任意保険基準|保険会社独自の社内基準
任意保険基準は、各保険会社が独自に定めている社内基準です。
自賠責基準よりはやや高い金額が提示されることが多いものの、保険会社によって算定方法や金額が異なるため、一概に金額を比較することはできません。
また、被害者が自分で交渉を行う場合、提示額が妥当かどうかを判断するのが難しいことがあります。
このため、任意保険会社の提示額をそのまま受け入れる前に、弁護士に内容を確認してもらうことが望ましいです。
裁判基準(弁護士基準)|最も高額な基準
裁判基準(弁護士基準)は、過去の裁判例をもとに裁判所や弁護士が用いる最も高額な基準です。
実際の目安としては、
- 14級
- 約110万円
- 12級
- 約290万円
が認められるケースが多く見られます。
この基準は、実際に生じた精神的苦痛や生活への影響をより適切に反映するため、被害者にとって最も有利な基準といえます。
弁護士に依頼すれば、裁判基準に基づいた正当な賠償金を請求できるため、保険会社の提示額が低いと感じる場合には、弁護士への相談が有効です。
後遺障害で悩んでいるときは早めに専門家へ
後遺障害の等級認定は、医師の診断内容や申請手続きの方法によって結果が変わることがあります。
痛みやしびれが残っているのに認定されなかった場合でも、適切な対応をすれば再申請によって認定されるケースもあります。
「この金額が正しいのかわからない」「後遺障害に認定されなかった」といった悩みをお持ちの方は、早めに専門家に相談してください。
弁護士が介入することで、適正な等級認定と適正な賠償を受けられる可能性が高まります。