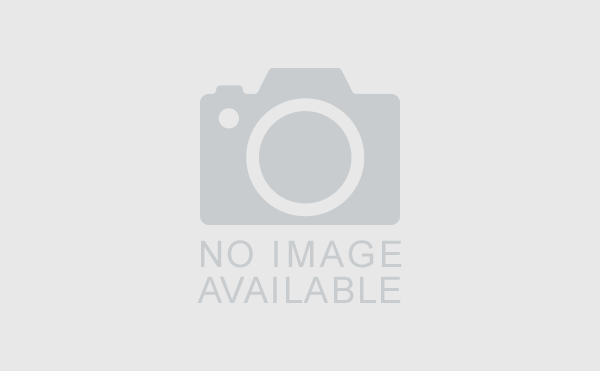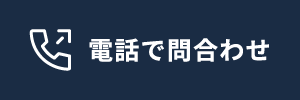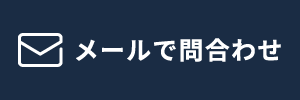佐賀で交通事故の後遺障害申請なら|経験豊富な弁護士がサポート
後遺障害等級認定までの基本的な流れ
後遺障害の等級認定は、交通事故による怪我が「症状固定」となった後に行われます。
ここでは、後遺障害等級認定までの一般的な流れを解説します。
1. 症状固定の判断
まず、医師が治療の経過を踏まえて「これ以上の改善が難しい」と判断した時点で症状固定とされます。
通院の終了時期ではなく、医師の診断に基づいて決定される点が重要です。
2. 後遺障害診断書の作成
症状固定後、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
この診断書は認定の根拠となる非常に重要な書類であり、症状や可動域制限、神経症状などが正確かつ具体的に記載されていることが求められます。
後遺障害の認定結果は、診断書の内容や申請書の書き方によって大きく変わることがあります。
医師の作成する診断書が必ずしも有利な内容になるとは限らないため、作成前に弁護士へ相談しておくと安心です。
3. 申請手続き(事前認定または被害者請求)
申請の方法には、次の2種類があります。
- 事前認定
- 加害者側の保険会社が申請手続きを代行する方法
- 被害者請求
- 被害者本人または弁護士が直接、自賠責保険会社へ申請する方法
申請の際は、必要書類を添えて加害者側が加入する自賠責保険会社に提出します。
実際の等級認定調査は、損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所が行います。
弁護士が代理人として被害者請求を行う場合、診断書や資料を適切に補強できるため、事前認定よりも有利な結果が得られる可能性があります。
4. 認定結果の通知
申請後、通常は2か月ほどで後遺障害の等級が決定し、通知が届きます。
認定結果に納得できない場合には、「異議申立て」を行って再審査を求めることも可能です。
認定を受けるための重要なポイント
後遺障害の認定を受けるためには、次の3つのポイントを意識することが大切です。
1. 医師との連携を密にする
医師が正確かつ詳細に後遺障害診断書を作成することが認定の大前提です。
自覚症状だけでなく、MRIやX線などの他覚的な所見があると、認定の可能性が高まります。
違和感や痛みがある場合は、診察時に具体的に伝えるようにしましょう。
2. 通院実績と整形外科での診察
整骨院(接骨院)の通院のみでは、後遺障害として認定されにくい傾向があります。
治療期間中は、整形外科を定期的に受診し、医師の診断を継続的に受けることが大切です。
医師による医学的な記録が認定の大きな裏付けになります。
3. 日常生活での支障を記録しておく
家事や仕事に支障が出ている場合は、その内容を日々メモしておくことをおすすめします。
「洗濯物を干すのがつらい」「長時間の運転ができない」など、生活の中で感じる不便さを具体的に残しておくと、医師に症状を説明しやすくなり、診断書の内容にも反映されやすくなります。
弁護士に相談すべき理由
後遺障害の等級認定は、医師の診断書や申請手続きの内容によって結果が大きく変わります。
弁護士に相談することで、次のようなサポートを受けられます。
- 後遺障害診断書のチェック・修正依頼
- 被害者請求における書類の精査と補強
- 「非該当」とされた場合の異議申立て対応
適切な準備とサポートを受けることで、より正確で有利な認定結果につながる可能性があります。
後遺障害の申請を検討している場合は、早い段階で弁護士に相談することが重要です。
弁護士なら誰でもいい?
後遺障害の等級認定に関する申請や異議申立ては、交通事故分野に精通した弁護士でなければ適切に対応できないことがあります。
医療記録の読み取りや、自賠責基準・任意保険基準の違いを理解していないと、適正な等級認定を受けるチャンスを逃すおそれもあります。
交通事故や後遺障害の経験が豊富な弁護士であれば、診断書の内容確認や医師への修正依頼、必要な書類の収集などを的確にサポートし、有利な結果につなげることが可能です。
そのため、「弁護士であれば誰でも同じ」と考えず、交通事故や後遺障害に詳しい弁護士を選ぶことが重要です。