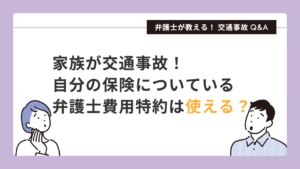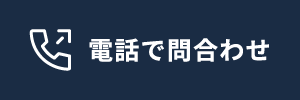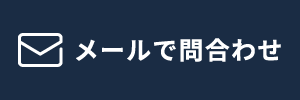症状固定とは何か?
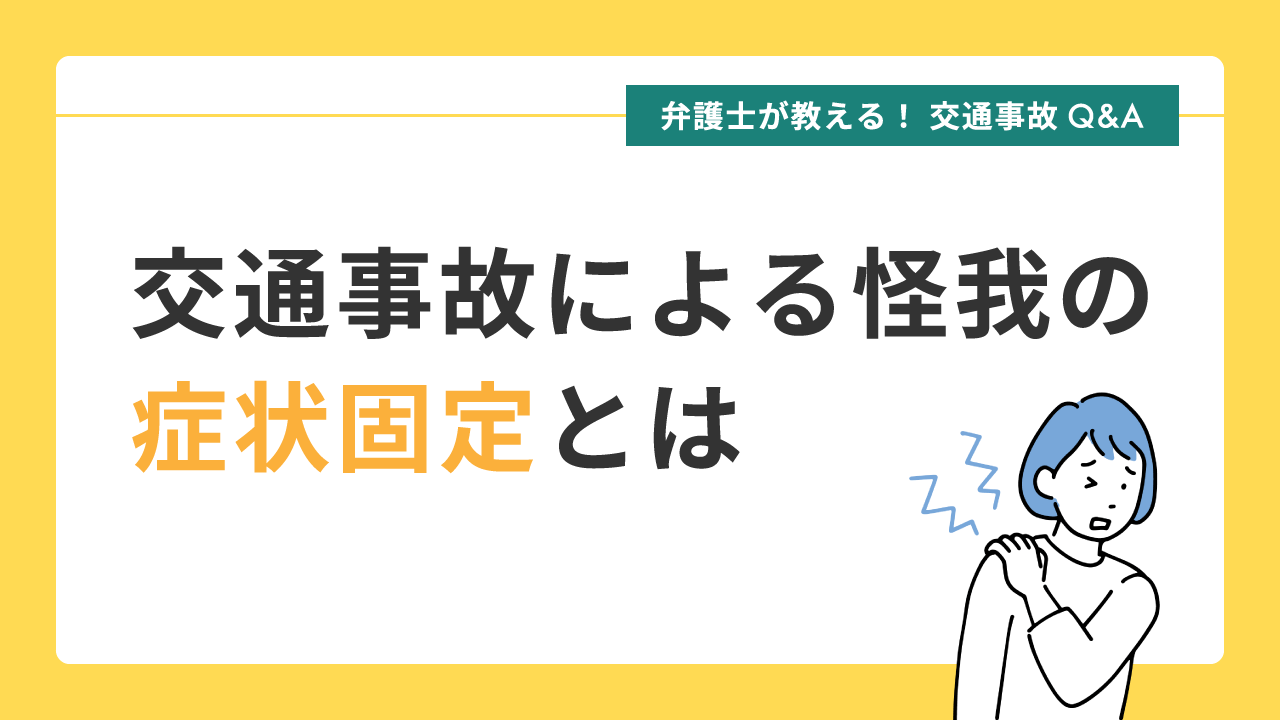
症状固定とは
交通事故でケガの治療を続けていても、症状の改善が期待できなくなる時期があります。
その状態を「症状固定」といいます。
症状固定とは「それ以上治療を続けても症状が良くも悪くも変わらない状態」を指します。
症状固定の時期については、担当医師から診断されるケースが一般的です。
さらに、症状固定の判断には法律的な意味も加わり、ケガの治療と後遺障害に対する賠償との区切りをつける役割を担います。
なぜ症状固定が重要なのか
症状固定によって、損害賠償の区分が「傷害分」と「後遺障害分」に分けられます。
- 症状固定前(傷害分)
- 請求できる費目:治療費、入通院の交通費や付き添い看護費、休業損害、入通院慰謝料など
- 症状固定後(後遺障害分)
- 請求できる費目:後遺障害慰謝料、逸失利益など
症状固定を早まると、治療費や休業損害の支払期間が短くなり、結果的に受け取れる補償額が減ってしまう可能性があります。
被害者の適切な保障のためには、症状固定時期の判断が重要です。
誰が症状固定を判断するのか
原則として、症状固定の判断は主治医が行います。
事故後の症状や治療過程を最もよく把握している立場だからです。
ただし、損害賠償においては法的な判断も関わるため、最終的に裁判所が認定するケースもあります。
たとえば、主治医の判断よりも早期に症状が安定していたと裁判所が認めれば、症状固定日が前倒しされることもあり得ます。
注意すべきポイント
- 保険会社から症状固定を促されたら要注意
-
保険会社は示談交渉や費用負担の節約のため、治療の途中でも「そろそろ症状固定」と治療費の打ち切りを打診することがあります。
しかし、それが医学的に正当な判断とは限りません。
- 治療継続が必要な場合は主治医に説明を求めて対応を
-
主治医が「治療継続が相当」と判断すれば、症状固定とはされません。
通院を続けたい、改善の見込みがあると考える場合、医師の意見をしっかり記録しておきましょう。
- 症状固定のタイミングを誤ると補償額が変わる
-
たとえばむちうちでは、事故から6か月以上通院しないと後遺障害として認められないこともあります。
早すぎる症状固定の判断は損害の軽減につながるおそれがあります。
- 症状固定後もまれに治療費が認められることもある
-
たとえば、症状固定後も症状が悪化するリスクが高く、治療を続けないと状態が維持できない場合には、例外的に治療費の請求が認められることもあります。
弁護士への相談が賢明な判断を下す手助けになる
症状固定の適切な時期や内容、後遺障害認定の方向性など、不安や判断に迷ったらまず専門家へ相談すると安心です。
弁護士であれば損害賠償請求の目線から適切に判断や交渉を進められます。
まとめ
- 症状固定とは、医学的に改善が見込めない状態で治療の区切りとされるタイミングです。
- 損害賠償の区分について、症状固定前は「傷害分」、後は「後遺障害分」として請求内容が切り替わります。
- 症状固定は基本的に主治医が判断し、争いになれば裁判所が判断することもあります。
- 保険会社の判断に流されず、主治医の意見をもとに適切に判断する必要があります。後遺障害認定の時期や症状固定のタイミング次第で損害額に大きな差が出ます。
- 適切な症状固定時期の判断や賠償請求の方向性を整理して、適切な補償をうけるためにも、交通事故に注力する弁護士にご相談ください。